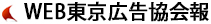広い社会と子どもをつなぐ活字
メディアビジネス 事業運営センター
紙面編成部 部長
岡村 博史
「習慣」と「慣習」、漢字の語順が前後すると意味が異なります。辞書等を引くと「習慣」は個人的、「慣習」は地域・社会的というように、用いる範囲の大きさに違いを感じ取られます。
個人的な「習慣」ですが、初めて新聞を読んだのは4歳くらい。といっても、好きな番組を探すためテレビ欄を見ていたくらいです。東京・兵庫・岡山・新潟で育ち、各地の社会科見学で新聞輪転機の迫力に驚いたり、友人が展覧会で賞をとった記事をおうちで額にいれて大事に飾っていたりと距離が近づいていきます。興味が増して複数紙をめくり、そこから得た情報から世界の広さを感じ、さらには新聞読者モニターに参加しました。やがて大学生になり、同世代があまり新聞を読んでいないことにふと気付きます。これが今から概ね四半世紀前の話。
「広い社会と子どもをつなぐのは活字」との思いから、大学卒論は童話作家の斉藤洋先生について書こうと思い立ちました。この方の作品、例えば、ストーリーの中に子どもと経済が絶妙に組み込まれていて、さらには言葉遊びも詰まっており、つなぐヒントがあると考えたからです。
卒業後に新聞広告の仕事に携わることができて、親子で読める紙面について考えました。「児童書企画」や、「ある機械部品が身近な多くの場所で活躍する姿を例えも用いて解説するコラムシリーズ」、また「企業と環境問題について小学校で授業する企画」などを色々な方々のご協力で実施できました。いずれも将来の新聞読者である子どもたちと早く接点をもって生涯ファンになってくれたら、という思いからでした。
ようやく話は現代に戻ってきますが、親になってからは子どもたちへの読み聞かせに勤しみました。活字が好きになって新聞を読んでくれたら、という願いを込めて。
文部科学省は2022年に第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」を策定し、小学校は2紙、中学は3紙、高校は5紙設置目安となるよう取り組んでいます。20年時点で、児童・生徒の閲覧用に新聞を置く公立小が56%で平均1.6紙、公立中も同じく56%で平均2.7紙。
子どもたちが新聞、また本の活字に触れることが「慣習」となって、そこから多くの出会いや知識を得て、何かのきっかけになることを期待しています。新聞広告紙面の審査を通じて、読者に伝える情報の一つとしてお役に立てたら、これほど嬉しいことはありません。